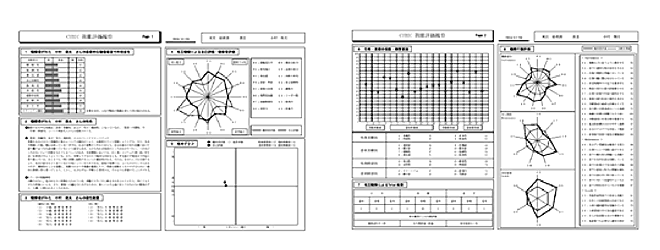CUBIC個人特性分析は、個人の資質や特性を「性格」「意欲」「社会性」「価値観」などの側面から評価すると共に、職業適性を5段階によって判定し、どこに配置するのが良いか具体的に分かりますので、まさに新卒・中途採用の職業/採用適性検査として最適です。 また、「現有社員」も受検することで、そのデータを基に必要な人物像を適性の面から割り出し、"会社が求め、必要とする人物像"、即ち自社の基準づくりを行うことができ、こうした自社基準値を採用判定基準にも役立たせることができます。
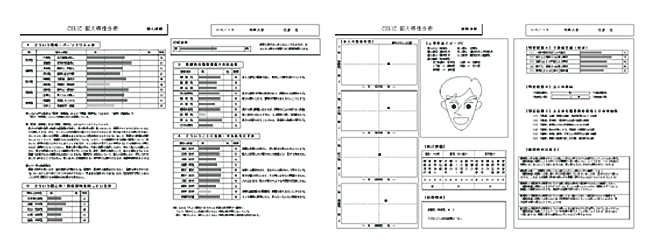
職務内容によっては、その職務に必要と思われる能力が欠けていては、安心して仕事を任せることはできません。性格面での適性を把握すると同時に、必要な能力を備えているかどうかを確認しておくことは、採用面で非常に重要な要素です。 CUBIC の能力検査は、採用時に各人の基礎能力を把握するのに最適です。 科目は『言語』、『数理』、『図形』、『論理』、『英語』の5つで7種類のバージョン(英語のみ4種類)にてご提供しています。 尚、基礎能力検査は1科目から数科目までご自由に組み合わせていただき、中学卒業レベルから大卒・中途採用レベルまで、幅広くご利用いただけます。
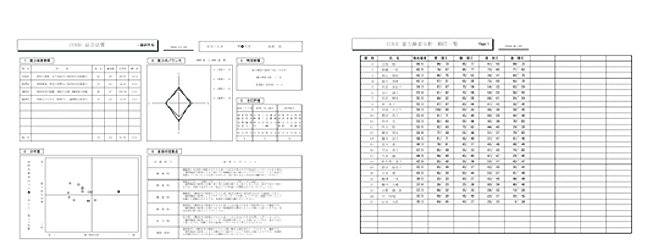
個々の社員特性をとらえ、人材を適材適所に配置させ活躍させることは、企業を成長させ、活性化させるために欠かせません。
CUBICでは、自己評価と他者評価の2側面から個人の特性をビジュアル的にとらえることで、その人物の良い点や努力を要する点を適性の面から浮き彫りにします。それらをふまえた上で、社員の教育や指導、あるいは配置転換等によってその人材の有効活用を実現します。
職場における現実の行動面から、個人の適性や能力構造を「性格」「意欲」「社会性」「価値観」などの側面から客観的に分析します。同時に「仕事に立ち向かう姿勢」や「組織だって仕事を進める能力」なども測定しますので、能力開発等を効果的にすすめる補助データにもなります。
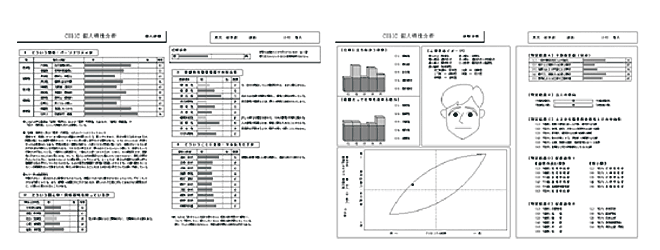
現有社員分析における「自己分析シート」は、個人特性分析の結果を本人にフィードバックし、本人と上司が今後の開発目標を、共通の観点で立てるために有効です。(現有社員分析の際のみ)
個人特性分析では、評価する観点からかなり直接的な表現も用いられていますが、自己分析シートは、受検者が自分の弱み・強みを簡潔に理解できるように作成しています。
この「自己分析シート」を活用することにより、自己のこれまでの行動パーターンを振り返り、具体的になにをどう変えていくべきかを考える研修等に活用することも可能です。
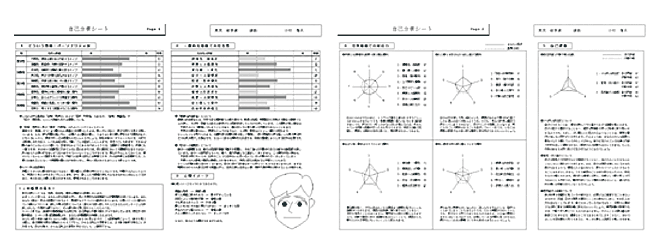
従業員が働きつつ、どういうことを感じ考えているのかなど、組織の現状と問題点を客観的データとして出力。分析結果は、風土厚生面、職務遂行面、人間関係面、組織構造面、会社評価の5つに分類された総合結果と、部署、役職、世代、勤続年数を切り口とした傾向分析により出力され、問題点の明確化と原因追究をはかります。
CUBICの「組織活力測定」とは、一般的にいうと「ES:EmployeeSatisfaction(従業員満足)」調査のこと。従業員が仕事を通じて、どの程度満足を得ているか、さらに組織がどの程度戦略に影響を与える業務を実行しているかを把握するためのものです。これを定期的に行うことによって、従業員の満足度合いだけでなく、方針の浸透度合いや業務遂行に必要な情報の充実度合いなどを定量的に把握することができます。
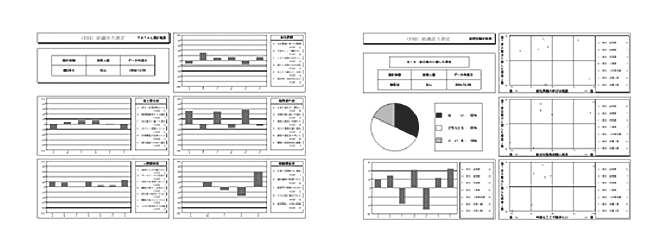
社員の対人関係に対するあり方を測定することにより、社員のエネルギーが仕事の目標遂行に向かっているのか、あるいは人間関係や環境に消耗されているのかを分析します。部署・年代ごとに社員が要求する管理者像や管理者として必要な行動が明確化され、管理者と社員の関係を明確にすることが可能です。
CUBICの「環境適合測定」とは、一般的にいうと「LPC:LeastPreferredCo-worker(最も都合のよくない仕事仲間)」調査のことです。一言で言えば、職場で一緒に働きたくないタイプのことであり、LPC得点で同僚の受容度、拒絶度が分かり、リーダーの指示行動を規定するものとして、LPCが大きな鍵となります。
CUBIC組織適合測定のメリットは、他社との比較ができいろいろな角度からの分析が可能です。2つに分類された集計結果と、部署、役職、世代、勤続年数を切り口とした傾向分析とグラフで表示される比較分析により出力されます。
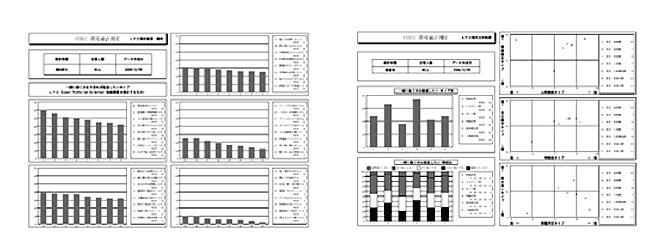
人がなぜそのような行動をとるのか、その理由はさまざまです。社員の行動の目的がどの方向に向かっているのか、その方向性を測定しようというのがモチベーション測定のねらいです。 社員が現在どのように働いているか、どの程度充実感を感じているかということ(現状)と、本当はどうしたいのか、何を重要視しているのか(理想)を比較することで、その社員の働き方に対する指向性を測定。測定される指向がどの程度重視されるか、その度合いを見ることにより、社員にとって何が動機付けとなるかが明らかになります。
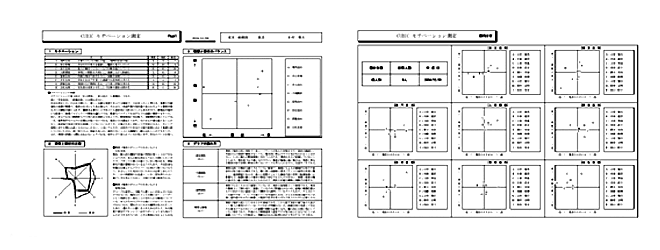
職務に関する上司・同僚・部下といった複数の目を通して人物評定を行うことにより、合理的・客観的に被観察者の人物像を描き出します。この観察結果に自己評価を交えることで、能力の特徴や持ち味を自己点検する資料となります。さらに各自の能力に応じた育成・開発の方向性を見つけることができます。